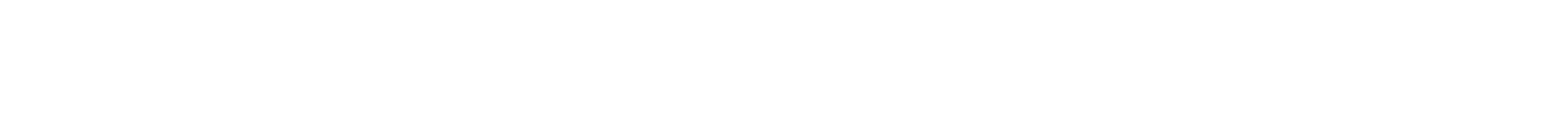文化人類学は、人間というややこしい存在について、できるだけその複雑さを温存しながら理解しようとする学問です。
多くの社会科学は、人間のある性質を理解するために、できるだけノイズとなる外部要因を減らす思考法を取ってきました。
だから、限定的な人間像を想定したうえで行動を数学的に計算したり、実験室のような周囲からの邪魔が入らない環境を設定したり、キー概念によって人間のある性質にだけ着目したり、様々な方法論を生み出してきたのです。
そうして解き明かされる発見は、私たちにとって目からうろこが落ちるようなものだったりします。 私たちの普段の生活には雑音が多すぎて、とうてい真実など見えてこないからです。 だからこそ、私たち自身もややこしくて割り切れない世界を少しでも整理してくれる 単純な答えというものを欲しているのかもしれません。
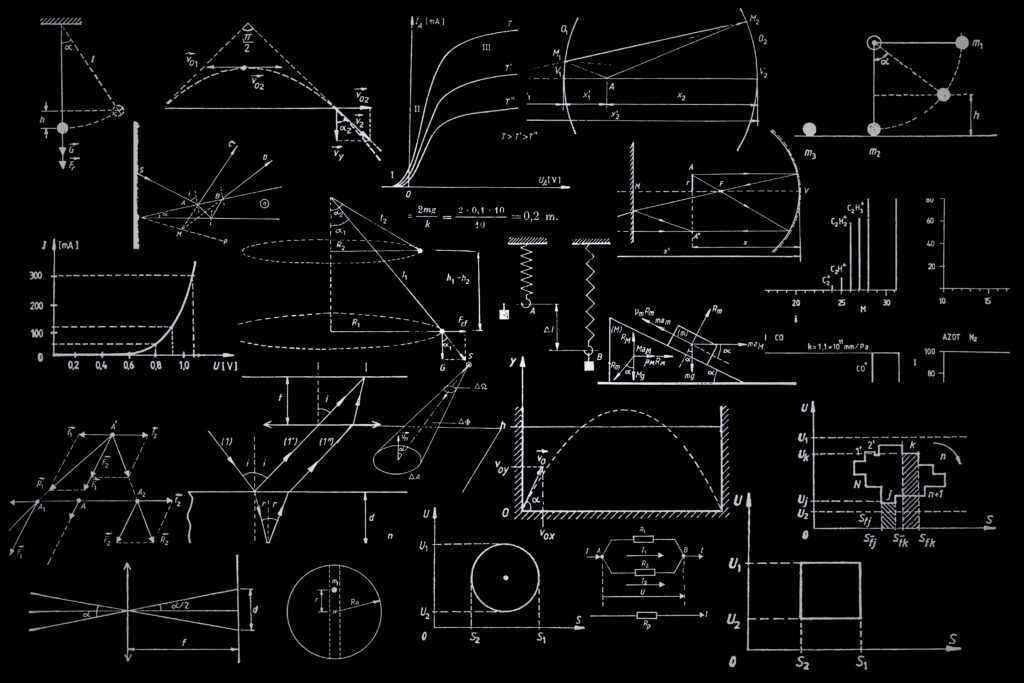

ところが、文化人類学はこうした大方の学問のやり方からずれています。なぜなら、世界の雑音を捨象することを良しとしないからです。
文化人類学はそのフィールドワークという研究方法に特徴があります。人びとが日々を過ごしているその場所へ行って話を聞くだけではなく、活動に参加してふるまい方を学び、土地の様子を観察し、政治経済的な情勢を計算に入れようとします。
こうした様々な側面を考慮に入れて物事を理解しようとする態度を、全体論的視角と言います。
全体論的視角のいいところは、現場の人びとの感覚からかけ離れていないところです。
私たちの日常は、一つの制度や一つの価値観によって支えられているわけではありません。思いがけない邪魔が入ったり、規則は守りつつも実際には柔軟に対応したり、マニュアル通りにはいかないことばかりです。
文化人類学はそれらを例外として処理せず、現場の日常として理解しようとする学問なのです。


だから、文化人類学の研究対象は多岐に渡ります。
どこか遠い国の聞いたこともないような民族集団について研究している文化人類学者も多くいます。
そうした人びとを外側から一面的に理解して取るに足らない存在として片付けることが偏見を生み出してきたからこそ、文化人類学は別の道を模索してきたのです。
他方で、最先端の科学技術や市場経済のグローバルな中心もまた、文化人類学の対象となってきました。
多くの学問によって理論化されてきた領域に入り混じる「雑音」に耳を傾ける時こそが、文化人類学者が本領を発揮する機会であるからです。

文化人類学は、あらゆる人間の日々の営みに寄り添おうとする学問です。
私たちには雑音に聞こえるものが、誰かにとってはメロディかもしれない。
私たちにとってメロディであるものが、誰かにとっては雑音かもしれない。
でも、人類学者にとってはすべてが音楽であり、そうした営みの複雑さや豊かさを知ることで、
他者に対する共感と敬意の手法を学んでいるのです。