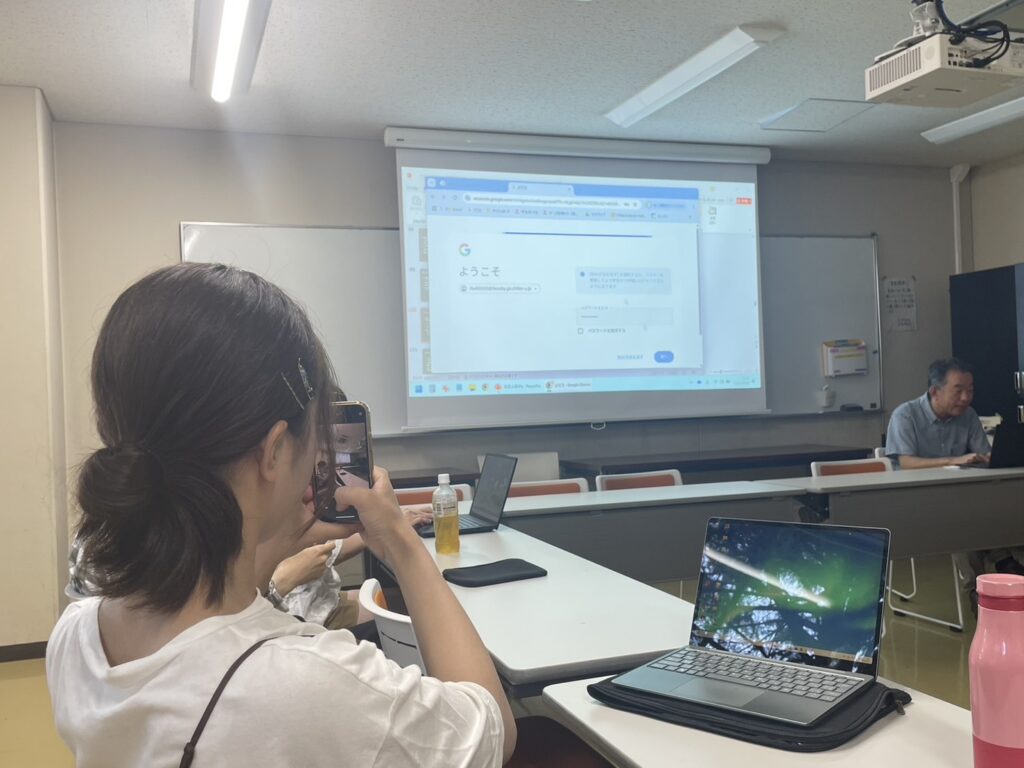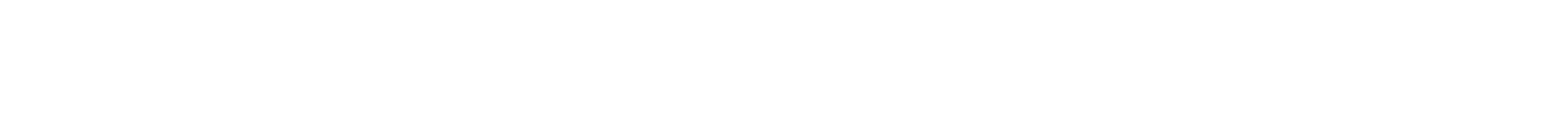今年度開講している学部授業科目は以下の通りです。
文化人類学基礎
概要
文化人類学の基礎的な概説。文化人類学講座の教員全員が順に担当し、文化人類学の研究領域、文化概念、研究方法などに関する講義を行う。
担当講師
小谷真吾、高橋絵里香
文化人類学調査概説A,B
概要
文化人類学においてフィールド調査は単なる方法論という以上の実践的意味を持つ。この授業では、フィールド調査の方法としての特性を概念的に説明することから始め、手紙の書き方からインフォーマントチェックに至るまでのフィールドワークの実践的進め方を示していく。
担当講師
小谷真吾、高橋絵里香
文化人類学研究法A,B
概要
文化人類学の各理論の特徴を把握しながら、その変遷と系譜を追う。現代の自社会にその理論をあてはめてみることで、批判と再評価を行いながら理解していく。
担当講師
高橋絵里香、康陽球
文化人類学概説B
概要
文化人類学の古典的民族誌を購読し、その発想と方法について学んでいく。主に、下記の二冊を取り上げる。
・ベネディクト・アンダーソン 2007(1983)『想像の共同体』書籍工房早山
・モーリス・レーナルト 1990(1947) 『ド・カモ』せりか書房
担当講師
浜田明範
文化人類学演習A,B
概要
私たちの生活は、多様な人や物、場所、自然環境などを巻き込んだ関係から成立しており、その関係の網の目が社会制度や歴史を形成してきた。人類学的な視点はその絡まり合いを紐解き、社会の仕組みや政治力学、現実の構成を理解する助けとなる。
前期では、こうした人類学的思考について、日本とベトナムを対象に社会史・生活史・地域史として書かれた2冊の文献を通じて学ぶ。授業は文献の講読、発表、討論を中心に進める。
後期では文化人類学専攻3年次学生を対象に、卒業論文のための研究計画作成を指導する。これまでの講義および演習で学んだ視点と知見を生かし、現代の多様な現象に対して文化人類学的な考察を行うための研究計画をたてる。
担当講師
康陽球、小谷真吾
文化人類学調査実習A,B,C,D
概要
フィールドワークは文化人類学の重要な調査方法である。この授業では、担当教員の指導を受けながら、フィールドワークの計画、実施プロセスを学生自身が体験する。こうした準備活動に基づき夏季休暇中に1週間ほどのフィールドワークを実施する。
担当講師
小谷真吾
医療人類学A
概要
依存・人口・スペキュレーションという3つのキーワードからエイジング(老いていくこと)について考えていく。文化人類学は近年、スペキュレイティブ・フィクション(SF)と思考のベクトルにおいて接近しつつある。それは、現在から直線的に伸びた先にある未来とは別の物語を構想するSF的営みが、近代的な世界秩序に異を唱えてきた文化人類学と呼応するからである。そして、老いについて考えることは、過去から未来へと広がっていく時間軸の中で私たちの世界を捉えていくことに他ならない。そこで、この授業ではスペキュレーションという思考実験を通して、他者と共に生きる未来を模索していく。
担当講師
高橋絵里香
生態人類学B
概要
生態人類学は、狭義の「生態学」的方法を用いた人類の多様性に関する研究、人間の生業活動に関する社会文化的研究、広義の「生態学」的問題意識に基づいた環境問題に関する研究など、幅広い内容を持つ学問である。「生態人類学b」では、日本における調査、研究を題材に講義を展開する。生業の多様性、環境問題、人口問題などの問題に関心をもつ学生を歓迎する。
担当講師
小谷真吾
生物人類学演習B
概要
人類学は、大きく文化人類学と自然人類学に分かれている。文化人類学を深く理解していくためには、もう一方の自然人類学の知識も不可欠である。本講義では、自然人類学の主な方法論について実践的に演習を行なっていく。具体的には、実際に狩猟採集活動に従事してもらい、その過程を記録することにより、労働生産性などを算出していく。
担当講師
小谷真吾
民族誌A
概要
人類学者のティム・インゴルドは、デザインや建築、思想といった幅広い領域から関心を集めている研究者である。近年は邦訳の出版ラッシュが続いており、どれから読めばいいか迷ってしまうような状況が続いている。そこで、この授業ではインゴルドの著作を横断的に購読していくことで、その思考の変遷をたどっていく。参加者は担当回についてコメントペーパーを作成し、ディスカッションを主導する。
担当講師
高橋絵里香
医療人類学A
概要
依存・人口・スペキュレーションという3つのキーワードからエイジング(老いていくこと)について考えていく。文化人類学は近年、スペキュレイティブ・フィクション(SF)と思考のベクトルにおいて接近しつつある。それは、現在から直線的に伸びた先にある未来とは別の物語を構想するSF的営みが、近代的な世界秩序に異を唱えてきた文化人類学と呼応するからである。そして、老いについて考えることは、過去から未来へと広がっていく時間軸の中で私たちの世界を捉えていくことに他ならない。そこで、この授業ではスペキュレーションという思考実験を通して、他者と共に生きる未来を模索していく。
担当講師
髙橋絵里香
芸能人類学
概要
「芸能」とは幅広い意味を持つ言葉であるが、上演が特定の個人の芸や能力と結びついていること、そしてそれが時空間を超えて歴史的に受け継がれていることを特徴とする。このような一見矛盾をはらんだ実践のあり方は、特定の社会における人びとの生活を、研究者の生活する社会にエスノグラフィという形で翻訳する人類学の実践と、パラレルに考えることができる。また近年では、人類学的な調査の成果を公演やワークショップの形で発表する「パフォーマンス・エスノグラフィ」といった研究手法も現れつつある。 以上を踏まえて、本授業では、「芸能人類学」を(「医療人類学」のような)人類学の下位区分としてのみならず、(「映像人類学」のような)人類学の研究手法としても捉え、イベントやプロジェクトの企画制作(アートマネジメント)を通じた人類学実践の可能性について考える。 具体的には、芸能や音楽を対象とした人類学的研究の潮流に関する理論編、その成果発表をワークショップやパフォーマンスに落とし込んだ先行事例を体験する実践編、そして各々の研究関心に基づいた企画案を考え発表する応用編を織り交ぜながら進行する。
担当講師
石橋鼓太郎
ジェンダーの人類学B
概要
「クィア」という概念は非常に捉え難い。ある面ではマイノリティ的な性の属性に関わるが、規範・世界に対する関係の取り方、思考の動きを指し示す動詞的・形容詞的な言葉でもある。人類学では「クィア人類学」という言葉が2000年代半ば頃から使われるようになっているが、これはいわゆる「クィア理論」の人類学への応用、としてのみでは捉えきれない背景と広がりを持っている(ただし人類学とクィア研究は長らく深く関わってきたし、その交差はもちろん重要である)。この授業は「クィア」に関わる(主に)人類学の文献に実際に触れることによって、「クィア人類学」とは何なのか、「クィア」という概念がどのような可能性・創造性・限界を持つのかについて、皆さんと一緒に考える場としたい。それにより、既にこの世界の中に(顕在的もしくは潜在的に)存在する、性に関わる多様さ・複雑さ・力・動きについてより豊かに理解するための方法を模索することを目指している。
担当講師
大村優介
人文科学専門英語
概要
This course will discuss world cultures. Students will read short articles each week. The articles will be from ethnographies. Ethnographies are in depth accounts of a society. Students will conduct field projects and learn about culture. Class activities will include pair work, group discussion, group activities, some lecture, films, individual and group projects, and other interactive activities. Because anthropology is a broad field, after the first few classes, students can select topics for a few classes. Students can choose their project topic. Homework for each class will be a reading assignment and to write a reflective journal discussing what you have learned and evaluating the reading and class activities. Class time will mostly be student interaction and some teacher lecture.
担当講師
WICKENS MATTHEW H.
卒業論文特別演習
概要
卒業論文の完成に向けた具体的指導を行う。
担当講師
小谷真吾、高橋絵里香